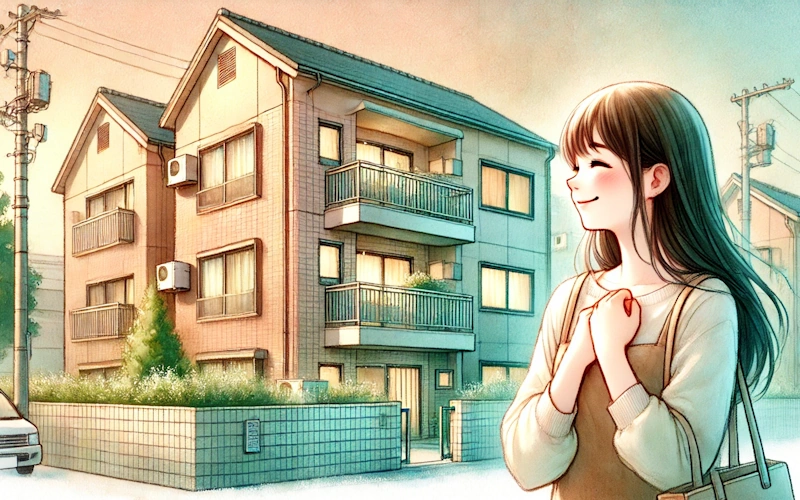「住宅の補助金や助成金は、持ち家を買う人だけのもの」――そんなイメージを持っていませんか?
実は、賃貸住宅に住んでいる人にも利用できる住宅関連の支援制度は、国・自治体・福祉分野などを中心に数多く存在します。
たとえば、家賃の補助、入居支援、バリアフリー改修の補助、災害時の住宅支援など、対象となる制度は年齢・世帯構成・収入状況・地域によって多種多様。
とくに、子育て世帯・ひとり親世帯・高齢者・障害者・離職中の人など、生活の変化に直面している人にこそ活用してほしい支援が揃っています。
本記事では、2025年5月時点で利用可能な「賃貸住宅でも使える住宅関連の補助金・助成金制度」を、初心者にもわかりやすく詳しく解説。該当する制度を知っているかどうかで、家計や暮らしの安定度は大きく変わります。
少しでも住まいの不安や負担を軽くしたいと考えている方は、ぜひ最後までチェックしてみてください。
もくじ
- 1 1. 住宅確保給付金
- 2 2. 家賃低廉化補助事業(セーフティネット住宅)
- 3 3. 自治体独自の家賃補助制度
- 4 4. 若者・子育て世帯向け家賃助成(自治体ごと)
- 5 5. ひとり親家庭向け家賃補助制度
- 6 6. 高齢者向け家賃助成制度(自立支援・居住安定目的)
- 7 7. 障害者向け住宅支援制度(家賃補助・入居支援)
- 8 8. 生活保護制度における住宅扶助
- 9 9. 住居支援法人による住宅確保要配慮者支援制度
- 10 10. 被災者向け応急仮設住宅・家賃補助制度
- 11 11. 離職者・失業者向け緊急住宅支援制度(自治体ごと)
- 12 12. 地方移住者向け賃貸住宅家賃補助制度
- 13 13. 地方創生・UターンIターン支援に基づく家賃助成
- 14 14. 自治体の子育て世帯向け民間賃貸住宅改修費補助制度
- 15 15. 賃貸住宅のバリアフリー改修に対する補助制度(高齢者・障害者対象)
- 16 「持ち家じゃないから関係ない」と思わずに、賃貸でも使える支援を活用しよう
1. 住宅確保給付金
住宅確保給付金は、離職や収入減少などにより住居を失う恐れのある人に対して、一定期間家賃相当額を支給する制度です。
生活困窮者自立支援制度の一環として全国の自治体で実施されており、特にコロナ禍以降、利用者が急増しました。
賃貸住宅に住み続けるための「家賃を補助する制度」であり、住居の安定を第一に支援する内容です。
就労支援とセットで行われるため、ハローワークなどとの連携も含めて、一定の活動要件を満たすことが求められます。
対象者の主な条件
- 離職・廃業後2年以内、または給与などの著しい減少により住居喪失の恐れがある人
- 一定の収入基準・資産基準を満たす世帯
- 原則として求職活動を行う意思と能力がある人
補助内容(2025年時点の目安)
- 支給額:家賃全額または上限内の額(地域の住宅扶助基準に基づく)
- 支給期間:原則3か月(最大9か月まで延長可)
- 家主への「代理支給」が原則(本人には直接支給されない)
申請はお住まいの市区町村の自立相談支援窓口で受け付けており、申請書・収入証明・通帳コピーなどの書類が必要です。
緊急性が高い場合は早めの相談をおすすめします。
2. 家賃低廉化補助事業(セーフティネット住宅)
「家賃低廉化補助事業」は、住宅確保が困難な人向けに、登録された「セーフティネット住宅(住宅確保要配慮者専用賃貸住宅)」に入居することで、家賃の一部を軽減する制度です。
国と自治体が連携して行っており、主に高齢者・障害者・子育て世帯・低所得者などが対象です。
この制度は住宅そのものに対する補助であり、入居者にとっては「家賃が安く設定された物件に入居できる」ことが最大のメリットです。
対象者の主な条件
- 高齢者・障害者・子育て世帯・住民税非課税世帯など
- セーフティネット住宅に入居すること
- 家賃が支払い困難な状況にあること
補助内容の例
- 月額1〜2万円程度の家賃補助(自治体により異なる)
- 補助期間:数年間の継続支給も可(条件付き)
- オーナー(貸主)への家賃分補填という形で支給
詳細は各自治体の住宅課または建築指導課などで案内されています。
登録住宅のリストや、補助対象となるかどうかの事前相談が可能です。
3. 自治体独自の家賃補助制度
国の制度とは別に、多くの自治体が独自に家賃補助制度を設けています。
これは、若者の定住促進や人口流出防止、子育て支援、ひとり親家庭支援など、地域ごとの課題に対応するための施策として展開されています。
制度の内容は市区町村によって異なり、補助対象者や金額、支給期間にばらつきがあります。
中には新婚世帯やUターン世帯、単身高齢者などを対象とした制度もあります。
対象者の一例
- 子育て世帯、若年世帯、新婚世帯
- 市外からの移住者、U・Iターン希望者
- 住民税非課税または所得制限ありの世帯
補助内容の例
- 月額5,000円〜30,000円程度の家賃補助
- 支給期間:1年〜最長5年間(自治体による)
- 引越し費用の一部助成とセットになることも
申請は自治体の住宅担当課または子育て支援課などで行います。希望する自治体の公式サイトで「家賃補助」や「住宅支援」などのキーワードで検索すると、募集情報が見つかります。
4. 若者・子育て世帯向け家賃助成(自治体ごと)
特に20〜30代の若年世帯や子育て中の家庭を対象に、家賃の一部を助成する制度が各自治体で実施されています。
これは少子化対策や地域定住を促す目的で、賃貸住宅に住む若年層を支援する内容となっています。
申請時に年齢や子どもの有無が重視される点が特徴で、新婚世帯向けの支援と重複して利用できるケースもあります。
対象となる主な条件
- 夫婦のいずれかが40歳未満(または35歳未満)
- 中学生以下の子どもがいる世帯
- 対象地域内への転入や居住を継続する意思があること
補助内容の例
- 家賃の1/3〜1/2相当(月額1万円〜3万円上限)
- 支給期間:1年〜3年程度が一般的
- 住民登録・所得条件の確認が必要
自治体によっては、同時に「子育て応援手当」「医療費助成」なども展開しており、複数の支援策を組み合わせることで生活コストを大きく削減できる可能性があります。
5. ひとり親家庭向け家賃補助制度
ひとり親家庭にとって、毎月の家賃負担は家計を大きく圧迫する要因のひとつです。
こうした家庭を支援するために、多くの自治体が「ひとり親世帯向け家賃補助制度」を設けており、住居の安定確保と生活再建の一助となっています。
この制度は児童扶養手当や就学援助と並んで支援の柱とされており、特に低所得世帯にとっては大きな助けとなります。
対象者の主な条件
- 児童扶養手当を受給しているひとり親世帯
- 賃貸住宅に居住しており、家賃負担が重いと認められる場合
- 就労または求職中で、生活自立の意欲があること
補助内容の例
- 月額5,000円〜20,000円の家賃補助
- 支給期間:原則1年(更新・延長可)
- 世帯の収入・就労状況により変動あり
申請には、児童扶養手当証書や収入証明書、賃貸契約書などの提出が必要です。
制度の有無や補助額は自治体によって異なるため、住んでいる地域の福祉担当窓口で早めに相談するのが確実です。
6. 高齢者向け家賃助成制度(自立支援・居住安定目的)
高齢者が安心して暮らせる住まいを確保するために、多くの自治体では「高齢者向け家賃助成制度」を設けています。
特に年金収入のみで生活している単身高齢者や、高齢夫婦世帯にとって、家賃の支払いは大きな負担です。
この制度はそうした経済的困難を抱える高齢者に対して、家賃の一部を補助することで住まいの安定を図ることを目的としています。
自治体によっては、高齢者専用住宅やシルバーハウジングなどへの入居支援とも連動しています。
対象者の主な条件
- 65歳以上の単身または高齢夫婦世帯
- 住民税非課税または生活保護に準じる収入水準
- 自立した生活が可能で、施設ではなく賃貸住宅に住む意思があること
補助内容の例
- 月額5,000円〜20,000円程度の家賃補助
- 支給期間:1年ごとの更新型(継続可)
- 見守り支援や定期訪問と連携した制度もあり
申請は高齢福祉課や住宅課で行い、年金額や家賃、居住状況を確認する書類が必要となります。
住宅確保が難しくなってきた高齢者にとって、住み慣れた地域で暮らし続けるための貴重な支援制度です。
7. 障害者向け住宅支援制度(家賃補助・入居支援)
障害のある方が安心して地域で生活するための支援として、「障害者向け住宅支援制度」が自治体ごとに実施されています。
制度には、バリアフリー対応住宅の斡旋や改修費助成に加え、家賃補助や生活支援員の派遣などが含まれます。
一般の賃貸住宅に入居する際に、家賃補助が適用されるケースもあり、民間の空き物件を障害者に提供する「登録住宅制度」と連携している場合もあります。
対象者の主な条件
- 身体・知的・精神いずれかの障害を持つ人
- 障害者手帳を所持していること
- 日常生活において一部自立が可能な状況であること
補助内容の例
- 月額5,000円〜30,000円程度の家賃補助
- 支給期間:1年または3年ごとに更新(自治体による)
- 障害者の入居を拒否しない住宅とのマッチング制度も併設
申請は福祉課・障害福祉課で行い、障害程度区分や収入状況に応じた審査が必要です。
安心して暮らせる住環境の確保のため、制度の活用が強く推奨されます。
8. 生活保護制度における住宅扶助
生活保護制度の中でも「住宅扶助」は、最低限の居住の場を確保するために設けられた重要な支援です。
これは、住居を失うことなく生活を維持するために、家賃や共益費などの住宅費用を国・自治体が負担する制度であり、賃貸住宅に住む場合の支えとなります。
住宅扶助は生活保護の一部であり、住民票があり、資産や収入が一定基準を下回る人が対象となります。
対象者の主な条件
- 生活保護受給者(または受給申請中の人)
- 資産や収入が最低生活基準を下回っていること
- 家賃額が地域の基準額内であること
補助内容の例
- 実際に支払っている家賃を上限に支給
- 支給額:地域・世帯人数により異なり、上限は月額2万円〜5万円台
- 支払いは原則として大家への代理支給
申請は福祉事務所(ケースワーカー)を通じて行われ、住宅契約書・収入状況・資産内容の確認が行われます。
家を失うリスクがある方には最も強力な制度の一つです。
9. 住居支援法人による住宅確保要配慮者支援制度
「住居支援法人」は、住宅を借りにくい立場にある人々(住宅確保要配慮者)に対して、住まい探しから入居後のフォローアップまでを支援する制度で、国の認可を受けた法人が各地域に設置されています。
対象となるのは、低所得者・高齢者・障害者・ひとり親・被災者・外国人など、住まい探しで不利な状況にある人です。
家賃補助そのものではなく、入居支援や家主への説得、保証人代行、緊急時の相談対応などを通じて「入居の実現」と「定着支援」を行います。
対象者の例
- 住宅確保要配慮者(高齢者、障害者、ひとり親、低所得世帯など)
- 住居の確保が困難で、支援を必要とする人
支援内容
- 入居支援(物件探し・家主との調整)
- 保証人代行・家賃滞納時の相談対応
- 緊急通報システムの設置や安否確認支援
支援を希望する場合は、地域の住居支援法人または福祉窓口に相談することで対応が始まります。
家賃補助に代わる「実践的な住宅支援」として、多くの地域で重要な役割を担っています。
10. 被災者向け応急仮設住宅・家賃補助制度
地震や水害などの災害により住宅を失った人に対して、自治体では応急仮設住宅の提供や、民間賃貸住宅の家賃補助制度を実施しています。
これらは「災害救助法」または「被災者生活再建支援法」に基づく支援であり、突然の住まい喪失に対応するための緊急措置です。
対象者は、災害により住居を全壊・半壊・長期避難を余儀なくされた人であり、罹災証明書をもとに支援の適用が決定されます。
対象者の主な条件
- 自然災害により住宅を喪失・損壊した世帯
- 自治体による被災認定を受けていること
- 罹災証明の発行を受けていること
補助内容の例
- 応急仮設住宅の無償提供(原則2年間)
- 民間賃貸住宅に入居する際の家賃補助(上限あり)
- 家賃補助は月額3万円〜6万円程度(自治体により異なる)
制度の詳細は災害の発生状況に応じて随時変更されるため、被災時には速やかに自治体の災害対策本部または住まい再建相談窓口へ相談することが重要です。
11. 離職者・失業者向け緊急住宅支援制度(自治体ごと)
急な離職や失業により、住居を失うおそれのある人を対象に、自治体では独自の緊急住宅支援制度を設けている場合があります。
これは、住まいを失わないように一時的な家賃の補助や住宅提供を行うもので、生活再建の第一歩を支援するための重要な制度です。
住宅確保給付金と併用されるケースも多く、地域によっては、生活困窮者を対象とした短期入居施設の提供や、賃貸住宅入居時の敷金・礼金補助も用意されています。
対象者の主な条件
- 離職・失業から半年以内の人
- 収入・資産が一定水準以下
- 住居を失った、またはその恐れがある人
補助内容の例
- 家賃の一部または全額補助(月額2万円〜6万円)
- 一時的な入居施設(シェルター・市営住宅など)への住まい提供
- 敷金・礼金の補助、保証人支援
制度は市区町村の福祉課・生活支援窓口などで案内されています。
就労支援と併用されることが多く、ハローワークとの連携が前提となることもあります。
12. 地方移住者向け賃貸住宅家賃補助制度
地域活性化や人口減少対策の一環として、地方自治体では都市部からの移住者に対し、賃貸住宅の家賃補助を行う制度を設けています。
これは、移住直後の生活安定を目的として、主に若者世帯や子育て世帯に対して支援される内容です。
対象となるのは、市外・県外からの移住者で、一定期間その地域に定住する意思を持つ人です。
就業・起業と連動した支援策の一部として実施されることもあります。
対象者の主な条件
- 市外・県外からの転入者
- 移住後5年以内にその自治体に居住し続ける意思がある人
- 家賃の自己負担がある民間賃貸住宅に入居していること
補助内容の例
- 家賃の1/2または上限2万円〜5万円の補助
- 支給期間:原則1年間(最長3年間の自治体も)
- 転入時の引越し費用や転入促進金と併用可能な場合もあり
申請には転入前後の住民票、賃貸契約書、就労証明書などが必要で、制度の受付期間は年度ごとに異なります。
空き家バンクと組み合わせた物件選定が条件となっている地域もあります。
13. 地方創生・UターンIターン支援に基づく家賃助成
Uターン・Iターン(都市部からの地方移住)を促進するため、地方自治体では独自に家賃助成や住まい支援制度を展開しています。
これは、移住者が地元での就業・子育て・起業などを継続できるよう、住まいの安定を図る目的で設けられています。
自治体によっては、移住支援金とのセット支援、空き家活用事業、UIターン就職奨励金などと連携した包括的な制度になっていることもあります。
対象者の主な条件
- Uターン・Iターンに該当する移住者
- 自治体が定める就業・起業・定住条件を満たすこと
- 民間の賃貸住宅または空き家を活用した住宅に入居していること
補助内容の例
- 月額1万円〜3万円の家賃助成
- 支給期間:1〜3年間(更新・加算あり)
- 引越し費用や定住一時金を併用できる場合あり
申請には住民票の写し、移住元住所の証明、家賃支払証明、就業証明書などが求められます。
制度の詳細は各自治体の移住促進サイトで公表されていることが多く、窓口での相談も可能です。
14. 自治体の子育て世帯向け民間賃貸住宅改修費補助制度
子育て世帯が安全かつ快適に暮らせるようにするため、自治体によっては「賃貸住宅の改修費」に対する補助制度を設けている場合があります。
これは、借主の家族構成や子どもの成長に応じて、間取り変更や防音対策、危険箇所の修繕などを行う場合に、その費用を補助する制度です。
貸主の同意を得たうえで、子育てに適した住まい環境を整えることを目的としています。
対象者の主な条件
- 18歳未満の子どもがいる世帯
- 賃貸住宅に居住し、貸主の許可を得て改修を行うこと
- 所得制限や住民税非課税等の要件を満たすこと(自治体による)
補助内容の例
- 改修費の1/2を補助(上限10万円〜30万円)
- 補助対象工事:防音・バリアフリー・間取り変更など
- 設計費・工事費・材料費なども一部対象
申請には、賃貸契約書、改修内容の見積書、貸主の同意書などが必要です。
子どもが安全に暮らせる住環境を確保するための貴重な支援であり、自治体によっては対象世帯を限定せず広く募集している場合もあります。
15. 賃貸住宅のバリアフリー改修に対する補助制度(高齢者・障害者対象)
高齢者や障害のある方が安心して賃貸住宅で生活できるよう、各自治体では「バリアフリー改修」に対する補助制度を設けています。
これは、手すりの設置、段差の解消、浴室やトイレの安全改修などにかかる費用の一部を補助する制度です。
賃貸住宅における改修は、所有者(貸主)の同意が必須であるため、申請前にしっかりと確認を取る必要があります。
対象者の主な条件
- 65歳以上の高齢者または障害者がいる世帯
- 医師の意見書や介護認定などにより改修が必要と認められること
- 賃貸住宅で、貸主の改修同意が得られていること
補助内容の例
- 改修費の1/3〜1/2を補助(上限10万円〜50万円)
- 対象工事:手すり・段差解消・引き戸・滑り止め床材設置など
- 介護保険の住宅改修制度と併用可の場合もある
申請は市区町村の高齢福祉課や障害福祉課で行い、事前相談と現地調査が行われることがあります。
安心・安全な暮らしを確保するための有効な支援制度として、賃貸住まいの高齢者にも強く推奨されています。
「持ち家じゃないから関係ない」と思わずに、賃貸でも使える支援を活用しよう
住宅支援と聞くと「持ち家の購入支援」や「リフォーム補助」が思い浮かびがちですが、実際には賃貸住宅に住む人を対象にした補助制度も数多く用意されています。
それらの多くは、家賃負担の軽減や安心・安全な住環境の確保、入居・転居の支援、災害時の救済など、生活を支えるための実践的な内容となっています。
今回ご紹介したように、支援の内容や条件は自治体や制度によって大きく異なりますが、「情報を知っているかどうか」が支援を受けられるかの分かれ道になります。
多くの制度は申請が必要であり、申請しない限りは自動的に支給されることはありません。
自分や家族が今、どの制度に該当するのか。住んでいる地域ではどんな支援があるのか――まずは「調べてみること」から始めてみましょう。
そして、もし対象となる制度があるなら、迷わず活用することが、家計の安定と住まいの安心につながります。
賃貸に住んでいても、使える支援はたくさんあります。
暮らしに少しでも余裕と安心をもたらすために、必要な支援を上手に取り入れていきましょう。