「車は持っていて当たり前」——そんな価値観を一度見直してみませんか?
車を所有することには多くのメリットがある一方で、維持費や管理の負担も大きいものです。
最近では、カーシェアやレンタカーなど、車を「所有しない」選択肢も増えています。
今回は、あなたの生活スタイルに合わせて「本当に車が必要か?」を見極めるためのポイントをまとめました。
もくじ
車を持つことのメリットとデメリット
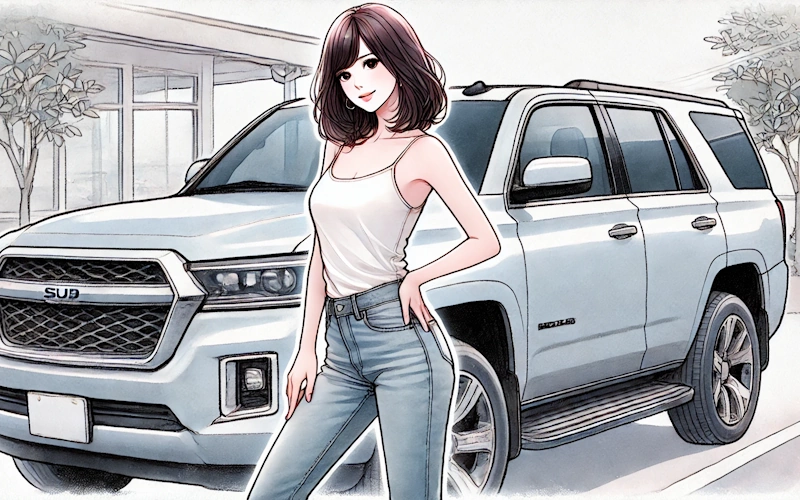
車を持つことは、便利さと安心感をもたらす一方で、経済的な負担やリスクも伴います。
特に日本では、都市部と地方で自動車の必要性が大きく異なり、「持っていて当たり前」と考えがちな人も多いのが現実です。
しかし、ライフスタイルの多様化やカーシェアの普及により、最近では「車を持たない選択肢」も増えてきています。
まずは、車を所有することで得られる主なメリットと、気を付けるべきデメリットを客観的に見直してみましょう。
メリット
- 移動の自由度が高い
- 重い荷物が楽に運べる
- 家族や友人と一緒に移動できる
- 天候に左右されない
- 緊急時に役立つ
- 行動範囲が広がる
- プライベート空間が持てる
- 趣味が広がる
- 時間の節約になる
- 仕事の幅が広がる
デメリット
- 維持費がかかる
- 初期費用が高い
- 駐車場代が発生する
- 交通事故のリスク
- 渋滞・混雑のストレス
- 環境負荷がある
- メンテナンスが必要
- 飲酒運転ができない
- 劣化・価値の目減り
- 盗難やイタズラのリスク
こうして見ると、車には日々の暮らしを豊かにするさまざまな利点がある一方で、決して小さくない負担があることも分かります。
特に、ライフステージや住んでいる地域、働き方によって「必要性の度合い」が大きく変わるのが車の特徴です。
今や、カーシェアやレンタカーなど代替手段も豊富に存在する時代。
メリットとデメリットをしっかり把握した上で、あなたの生活にとって本当に“持つ価値があるのか”を見極めることが大切です。
こんな人は「車なし」でも十分やっていける!

車は便利な反面、維持するだけで毎月かなりのコストがかかります。
特に最近は、カーシェアやレンタカー、電動自転車などの代替手段が充実しており、「車がなくても十分にやっていける」環境が整ってきています。
では、どんな人が“車なし生活”に向いているのでしょうか?
以下で詳しく見ていきましょう。
都市部在住で交通機関が発達している
東京都心部や大都市圏に住んでいる人は、電車・バス・地下鉄などの公共交通機関が充実しています。
これらを使えば、通勤や買い物、外出はほとんどカバー可能で、むしろ駐車場探しや渋滞のストレスがない分、車がない方が身軽です。
また、駅近物件に住んでいる場合は、生活圏がそもそも公共交通で完結するケースが多いでしょう。
通勤や日常の移動が徒歩・自転車圏内
オフィスや学校、スーパー、病院などの生活インフラが徒歩または自転車で行ける範囲にある場合、車の必要性はかなり低いです。
特に健康志向の高まりもあり、徒歩や自転車での移動は「運動不足解消」という副次的なメリットも。
生活圏がコンパクトにまとまっている人は、車がなくてもほとんど困りません。
年に数回しか車を使わない
「年に1~2回の帰省や旅行のためだけに車を維持している」という人は意外と多いものです。
しかしそのためだけに高額な維持費を払い続けるのはコスパが悪いと言えます。
必要な時にレンタカーを使えば、最新の車を短期間で利用でき、むしろ快適なケースも。
使用頻度が低い人は、思い切って「持たない選択」に切り替える価値があります。
カーシェア・レンタカーが利用しやすい環境
近所にカーシェアのステーションがある、またはレンタカーショップが充実している地域に住んでいる場合、車がなくても必要な時だけ借りるスタイルで十分対応可能です。
特に最近のカーシェアは、スマホで簡単に予約できる上、15分単位などの短時間利用もOK。
急な買い物や週末のお出かけにも便利です。
駐車場代が家計を圧迫している
都市部では駐車場代が月2~3万円を超えることも珍しくありません。
駐車場の確保自体が難しいエリアもあります。
こうした場合、車の所有そのものが“贅沢品”になりがちで、家計を見直すならまず駐車場代をカットするのが即効性の高い節約です。
実際、車を手放したことで「家計が劇的に楽になった」という声はよく聞きます。
その他、こんなケースも
- 単身世帯・一人暮らし:1人暮らしの場合、移動手段を柔軟に変えることができるので、車なし生活との相性が良いです。
- 高齢で運転に不安がある人:年齢とともに運転に不安を感じる場合、無理に車を維持するよりも、公共交通機関に切り替えた方が安全面で安心です。
- 環境意識が高い人:脱炭素や環境配慮の観点から、あえて車を持たない選択をする人も増えています。
このように、車が「必須ではない」ケースは意外と多くあります。
重要なのは、あなたの生活スタイルと照らし合わせて、本当に車が必要か、あるいは無理なく手放せるかを見極めることです。
「やっぱり手放せない…」が本当に必要か再確認しよう
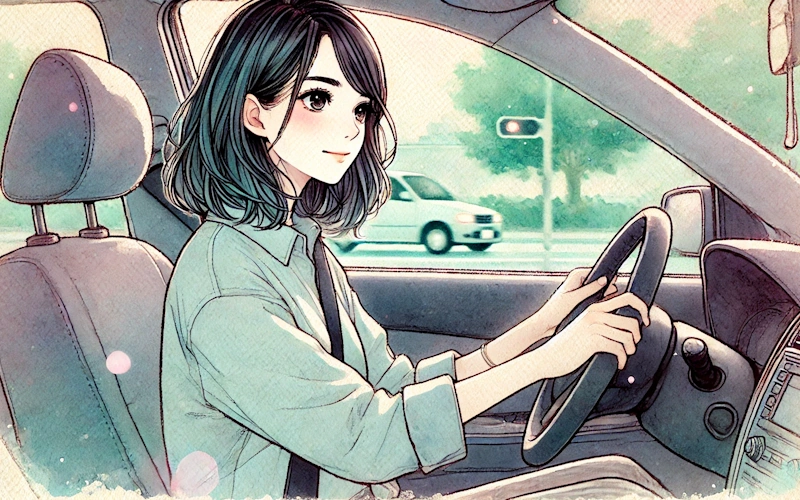
ここまで読んで「でも、やっぱりうちは車がないと無理!」と感じている方もいるかもしれません。
たしかに、生活スタイルや家族構成、地域によっては、車が不可欠なケースもあります。
しかし、その「本当に必要か?」をもう一度見つめ直してみることは、ムダな出費を防ぐうえで大切です。
ここでは、車が必要かどうかを再確認するための視点を紹介します。
子育てや介護など特別な事情がある?
小さなお子さんがいる家庭や、高齢のご家族を介護している場合、車は単なる移動手段ではなく“生活の命綱”になることがあります。
特に、保育園や習い事の送迎、急な発熱時の通院、介護施設への送り迎えなどは、車があると圧倒的にラクで安心です。
ただし、このケースでも「平日のみ必要」「週末だけ使う」など、使う頻度や状況を改めて見直してみると、カーシェアや地域の送迎サービスで代替できることも。
状況に応じて、所有と利用のバランスを考えてみましょう。
日常的に荷物が多い・長距離移動が多い?
例えば「仕事帰りにまとめ買いをして帰るのが日課」や「週末ごとに地方への出張・遠征がある」といった人は、車があると格段に便利です。
特に、大量の荷物を運ぶ、重量物を頻繁に扱うといったシーンでは、車なしだとストレスが溜まることも。
この場合も「どの程度の頻度で必要か」を冷静に考えることが重要です。
たとえば、週に1回程度なら電動自転車+宅配サービスを併用する方法もあります。
逆に「ほぼ毎日大量の荷物がある」という場合は、やはり車は不可欠でしょう。
災害時など“もしも”の安心感を重視する?
日本は災害が多い国。大地震や台風などの災害時、「車があるととりあえず避難できる」「プライバシーが守れる」「一時的な避難場所として使える」といった安心感があります。
特に地方では避難所が遠かったり、支援がすぐ届かないこともあるため、車が“命綱”になるケースも考えられます。
ただし、防災目的だけのために車を持ち続けるのは大きなコストがかかるため、代わりに地域の防災体制や家族の防災計画を強化するという方法もあります。
万が一の安心とコストのバランスを考えることが大切です。
運転そのものが好き・趣味の一環
「ドライブが趣味」「車いじりが生きがい」という人にとっては、車は単なる移動手段以上の存在です。
そうした場合、コストだけで「不要」と割り切るのは難しいかもしれません。
ですが、趣味として車を維持するなら、家計の中で“趣味費”として計上してしっかり管理することが重要です。
また、車を複数台所有している人は、「趣味車だけ残して日常使いはカーシェアにする」など、折衷案を検討しても良いでしょう。
公共交通が不便な地域に住んでいる
地方在住の方は、そもそも公共交通が少なく、車がないと生活が成り立たないケースもあります。
特に、バスが1日に数本しか来ないエリアや、最寄り駅まで車で30分といった地域では、車は“生活必需品”といえます。
ただし、この場合も「家族内で複数台持ちを見直す」「シェアカー制度を活用する」など、少しでもコストダウンできる工夫は考えられます。
まずは“使用頻度”を棚卸ししてみよう
「必要かどうか」を判断するには、まず直近1カ月で何回車を使ったか、その内容は何かを具体的に洗い出してみるのが有効です。その結果、
- 毎日使っている → 手放すのは難しい
- 週に1回程度 → 代替案を検討する価値あり
- 月1回未満 → 手放しても困らない可能性大
といった目安が見えてきます。
このように、「何となく必要」ではなく、「本当に必要か?」を冷静に考えることが、無駄な出費を見直す第一歩になります。
所有の理由が「安心感」だけの場合は、その安心感を他の方法で補えるかも検討してみましょう。
維持費を見える化。手放すとこれだけ節約できる!

「車は便利だけど、維持費が高い」というのは多くの人が感じていること。
でも実際、どれくらいお金がかかっているのか?をきちんと把握している人は意外と少ないものです。
ここでは、車を持つことで発生する代表的な維持費を具体的に見える化し、車を手放すとどれだけ節約できるのかを考えてみます。
自動車の年間維持費はどれくらい?
車の維持費は、次のような項目で構成されています。
| 項目 | 目安の金額(年間) |
|---|---|
| 駐車場代 | 12~36万円(都市部では50万円超も) |
| ガソリン代 | 6~18万円 |
| 自動車保険料 | 5~10万円 |
| 自動車税・重量税 | 3~5万円 |
| 車検・点検・メンテナンス | 5~10万円 |
| 消耗品(タイヤ・オイルなど) | 3~5万円 |
| 洗車・車内清掃など | 0.5~2万円 |
合計:おおよそ35万~85万円/年
特に都市部の場合は、駐車場代が家計の重荷になりやすく、これが車を持つかどうかの大きな判断材料になります。
車を手放すと何が浮く?
仮に都市部で月3万円の駐車場を借りていたとすると、駐車場代だけで年間36万円。
これにガソリン代や保険料、車検代を加えると、最低でも年間50万円近い維持費が発生します。
つまり、車を手放すことで単純計算で年間50万円前後の節約が実現できる可能性があるのです。
5年間で考えると250万円以上の節約にもなり、住宅ローンや教育費、老後資金の積み立てなど、他の大きな支出に回すこともできます。
車を持ち続ける場合との比較シミュレーション
例えば、月2回程度しか車を使わない場合、
- マイカー所有:年間維持費 約50万円
- カーシェア利用:月2回×5時間×3,000円程度=月6,000円・年間 約7万2,000円
このケースでは、年間約40万円以上の節約ができる計算です。
また、レンタカーの場合でも、1日8,000円×年10回借りたとして8万円程度。
維持費と比べると、依然としてコストメリットが大きいです。
維持費の“見えにくい出費”にも要注意
車を持つと、見えやすい費用だけでなく「突発的な出費」もあります。
- タイヤのパンク、バッテリー上がりなどの緊急修理費
- 車上荒らし・イタズラ対策としてのセキュリティ強化費
- 自動車事故の際の免責額や等級ダウン
これらは突然発生するため、予備費としてプラスαの負担が必要です。
見えにくい出費が意外と財布に響く…というのも車所有のデメリットの一つです。
浮いたお金をどう活用する?
節約できた維持費は、次のような使い道が考えられます。
- 教育資金や老後資金の積み立て
- 旅行や趣味への投資
- 家のリフォームやインテリアのグレードアップ
- 不測の事態への備え(緊急予備資金)
「車なし生活」で浮いたお金を見える形で有効活用することで、暮らしの満足度はむしろアップすることが多いです。
まずは“今の維持費”をしっかり把握
「車は必要」と思っていても、数字として維持費を見直すと驚くことが少なくありません。まずは、
- 月々いくらかかっているのか
- 年間トータルでいくら負担しているのか
をリストアップし、現実を「見える化」することから始めてみましょう。
その上で、カーシェアやレンタカー、公共交通など代替手段と比較してみると、より納得のいく判断ができるはずです。
車なし生活のリアル・利用できる代替手段

「車を手放したら本当に困るのでは?」と不安になる人も多いですが、実は現代の都市・地方を問わず、代替手段はどんどん増えています。
ここでは、車がなくても不自由なく暮らせるための代替サービスや工夫を詳しく紹介します。
カーシェア&レンタカーの上手な使い方
カーシェア
カーシェアは「使いたい時だけ借りる」新しいスタイル。
スマホで簡単に予約・返却ができ、24時間いつでも利用可能なサービスが増えています。
15分単位で使えるため、ちょっとした買い物や送迎にも便利です。
主なメリット
- 15~30分単位の短時間利用ができる
- 月額無料プランもあり、維持費ゼロ
- ガソリン代・保険料込みで安心
代表的なサービス例
- タイムズカー
- カレコ
- オリックスカーシェア
レンタカー
レンタカーは「1日単位で借りる」ときに便利。
旅行や長距離の移動時、荷物が多い時に重宝します。
最近は都市部の店舗だけでなく、駅前や商業施設にも設置され、より身近に。
ポイント
- 長時間・長距離利用に向いている
- 軽自動車から大型車、ワゴンまで選べる
- 定期的なキャンペーンでお得な時期も
電動自転車・バイクの活用
都市部・郊外を問わず注目度が上がっているのが電動アシスト自転車。
坂道もスイスイ、子どもを乗せるママチャリタイプもあり、日常の買い物や通勤に大活躍です。
電動自転車のメリット
- 初期費用以外ほぼ維持費なし
- 駐輪場の確保が簡単
- 健康的な生活をサポート
さらに、小型バイク(原付)は、短距離なら車の代わりとして十分使える選択肢です。
税金や保険料も車より圧倒的に安く、都市部でも利用しやすい点が魅力です。
タクシーアプリ&配車サービスを味方に
「急いでいる時」「夜遅い時」などに頼りになるのがタクシーや配車アプリ。
今やスマホで手軽に呼べて、クレジットカード決済や事前見積りもOK。
特に小さなお子さん連れや高齢者世帯には強い味方です。
代表的なアプリ
- GO
- DiDi
- Uber(都市部限定)
ポイント
- 迎車料金や割増料金の有無を事前確認
- クーポンや割引キャンペーンを活用
宅配サービスで買い物も快適に
車があると「まとめ買い」がラクですが、最近は宅配サービスが進化しており、重いもの・かさばるものは自宅まで届けてもらえるのが一般的に。
利用できる宅配サービス
- 食料品:ネットスーパー(イオン、イトーヨーカドーなど)、Oisix、コープ
- 日用品:Amazon、楽天、LOHACO
- ドラッグストア:マツモトキヨシ、ウエルシアなどが配達対応
また、冷蔵・冷凍品の宅配も増え、日常の買い物はほぼカバーできます。
宅配料も、一定額以上で無料になることが多いので、使いこなせば車以上に便利なケースも。
その他の便利な選択肢
デリバリーサービス(Uber Eats、出前館など)
外食が面倒な時も自宅まで料理が届くので、外出の手間が減少。
地域コミュニティの送迎サービス
地方自治体やNPOが運営している送迎バスや福祉タクシーも、見逃せないサポートです。
公共交通の割引制度
自治体によっては高齢者・障がい者向けに交通費の補助や割引があるので、コスト面でも有利に。
組み合わせて最適解を見つけよう
車なし生活が快適に成り立つかどうかは、これらの代替手段をどう組み合わせるかがカギです。
例えば、
- 日常は電動自転車+宅配サービス
- 雨の日や遠出はカーシェア&レンタカー
- 急ぎや夜間はタクシーアプリ
このように「所有しないけど、必要な時に賢く使う」ことで、車がなくてもストレスなく生活できます。
「不便では?」という先入観を持つ人も多いですが、代替手段を知り、組み合わせることで、むしろ無駄のないスッキリとした暮らしが実現できるケースも少なくありません。
あなたのライフスタイルに合わせて、最適な選択肢を見つけてみてください
「本当に必要か?」見極めのための3つの質問

ここまで読んで、車を持つか手放すか迷っている方も多いと思います。
最後に、あなた自身の状況を客観的に判断するための3つの質問を用意しました。
この問いかけを通じて、車が本当に必要かどうかをもう一度考えてみてください。
1年後も同じ生活スタイルを続ける予定か?
子どもの成長、転職、引っ越しなど、ライフスタイルは意外と変わるものです。
今は必要でも、1年後は不要になる可能性があるなら、短期的な対策(カーシェアやレンタル)で十分なケースもあります。
代替手段でほとんどカバーできないケースはあるか?
カーシェア、レンタカー、公共交通、自転車、宅配サービスなど、代わりになる方法をリストアップしてみましょう。
そのうえで「どうしても代替が難しい場面」がどれくらいあるかを冷静に見極めることが大切です。
家計・ストレス・安全面で“持つメリット”が上回るか?
お金の負担だけでなく、心の余裕や安心感も車を持つ価値の一部です。
維持費の高さだけで判断せず、総合的に「手放すよりも持ち続けた方が楽か?」を自問してみましょう。
ワンポイントアドバイス
すぐに決断するのが難しい場合は、「試しに3か月間、車なしで過ごしてみる」ことをおすすめします。意外な発見があったり、「やっぱりなくても平気!」と感じるきっかけになるかもしれません。

