家計簿を始めてみたいけど、手書きとアプリ、どっちがいい?
そんな疑問を持つ人は多いはずです。家計簿は継続が命。
だからこそ、自分にとって“使いやすいスタイル”を選ぶことが何よりも大切です。
この記事では、手書き家計簿とアプリ家計簿、それぞれのメリット・デメリット・向いている人の特徴を比較しながら、あなたにぴったりの家計簿スタイルを見つけるヒントをお届けします。
もくじ
手書き家計簿の特徴とメリット・デメリット
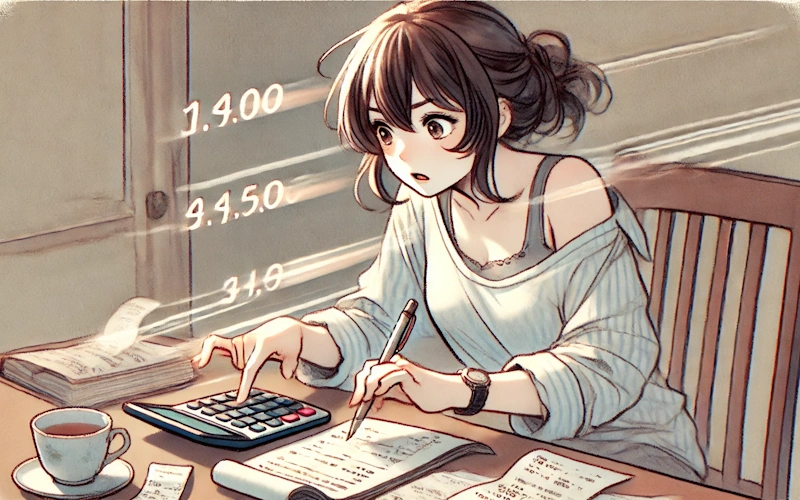
手書き家計簿は、ノートや家計簿専用帳を使って、自分の手で1つひとつ記録していくアナログな方法です。
最も基本的で歴史あるスタイルですが、その分「自分のペースで自由に記録できる」という特性を持ちます。
最近では、100円ショップや書店でさまざまなデザインの家計簿ノートが販売されており、シンプルな一覧表タイプから、週ごとの収支を細かく記録できるタイプまで、選択肢は非常に豊富です。
自分で枠を作る自由なノート式や、既に項目が印刷されているテンプレート式など、自分の性格や目的に合わせた使い方が可能です。
手書き家計簿のメリット
書くことでお金の使い方が“意識化”される
手で書くという行為には、思った以上に「記憶」と「意識づけ」の効果があります。
アプリでは流してしまいがちな「コンビニで無意識に買ったもの」「つい衝動買いしたもの」も、手書きで記録しようとすると「本当に必要だった?」と自問する習慣が生まれやすくなります。
自由にカスタマイズできる
表のレイアウトを自分で設計したり、メモ欄にその日の気分や節約の工夫を書いたりと、情報のまとめ方に自分らしさを出せるのが手書き家計簿の魅力です。
イラストやシールを使って「見ていて楽しいノート」に仕上げる
家族の予定や献立と一緒に記録して、暮らし全体を可視化する
振り返り欄を設けて、「何を反省したか」「来月への目標」などを書き込む
こういった自分だけの使い方ができるのは、デジタルでは得られないメリットです。
視覚的に情報が整理される
ノートを開けば「今月の出費」が一覧で見えるので、全体像が把握しやすく、比較・分析も自然にできます。
アプリのように複数の画面を開かなくても、「1ページで全体が把握できる」という安心感があります。
年代を問わず使いやすい
スマホ操作に不慣れな世代(中高年層やデジタルが苦手な方)でも、紙とペンさえあればすぐに始められる手軽さがあります。
手書き家計簿のデメリット
書く手間と時間がかかる
レシートを見ながら1件ずつ手で書き込むため、1回の作業にある程度の時間が必要です。
特に忙しい人にとっては、「書く時間が取れない」→「だんだん記録しなくなる」という悪循環に陥る可能性があります。
計算・集計はすべて手作業
月末の収支合計や、費目ごとの集計は電卓で行う必要があります。
アプリなら自動でグラフ化されるような分析も、手書きだと手間がかかるため、継続には根気が必要です。
紛失や管理のしづらさ
ノートは物理的なものなので、うっかり紛失したり、どこにしまったか忘れてしまうと情報が見られなくなります。
保管にもスペースが必要で、長年続けると複数冊になり、管理が面倒になる場合もあります。
外出中の記録が難しい
外出先で使ったお金をすぐに記録できず、後回しにしてしまい、後で思い出せなくなるケースも。
スマホのように「いつでも記録」できるわけではないのがデメリットです。
手書き家計簿は「丁寧に向き合いたい人」におすすめ
手書き家計簿は、スピードや効率よりも「じっくり向き合うこと」に価値を感じる人に向いています。
- お金の使い方を意識したい
- 日記や記録が好き
- 自分だけの管理スタイルを作りたい
という方にとっては、アプリ以上にしっくりくる可能性があります。
ただし、毎日の記録が難しい場合は、「1週間ごと」「月末だけ」など、自分に合った頻度で無理なく取り組むことが長続きのコツです。
家計簿アプリの特徴とメリット・デメリット

家計簿アプリは、スマートフォンやタブレットを使って、日々の収支をデジタルで記録・管理できるツールです。
多くのアプリには、次のような機能があります。
- 支出・収入の入力
- 費目別の自動分類
- グラフ表示による支出分析
- 銀行口座・クレジットカードとの連携機能
- 家族との共有機能(アプリによる)
代表的なアプリには「マネーフォワードME」「Zaim」「OsidOri」「LINE家計簿」などがあり、無料プランでも十分な機能を備えているものが多いです。
スマホに入れておくだけで、すき間時間に記録ができるため、忙しい現代人にとって非常に人気の高い選択肢となっています。
家計簿アプリのメリット
入力が簡単で自動化できる
家計簿アプリ最大の魅力は、「手間がかからないこと」です。
銀行口座・クレジットカード・電子マネーなどと連携すれば、支出が自動的に反映・分類されるため、手入力の必要が最小限に抑えられます。
レシート撮影による読み取り機能を搭載したアプリも多く、現金払いの記録すらカメラで済ませられるケースも。
これにより、家計簿が「毎日つける作業」から「自動で流れる情報を確認するだけ」に変わります。
支出の傾向がグラフで一目瞭然
アプリでは支出や収入を円グラフ・棒グラフなどで自動的に可視化してくれます。
月単位・週単位・カテゴリー別の支出割合が一目でわかり、
- 「食費が家計の○%を占めている」
- 「今月は外食が多め」
- 「娯楽費が先月より減った」
など、日常の“お金の使い方の傾向”が明確に把握できます。
時間や場所を選ばず入力・確認ができる
スマホ一台あれば、移動中・仕事の休憩時間・寝る前など、思い立った時にすぐ記録やチェックが可能です。
外出先のコンビニで使った支出をその場で入力することで、記録漏れを防ぎやすくなります。
通知機能で習慣化しやすい
多くのアプリには、「今日の記録を忘れていませんか?」というリマインド通知機能があり、家計簿が習慣になりやすい設計になっています。
また、予算オーバー時にアラートを出してくれる機能もあり、「使いすぎ防止」に役立つガード機能も充実しています。
家族やパートナーと共有できる(対応アプリの場合)
「OsidOri」や「Moneytree」など一部のアプリでは、夫婦・家族間で家計情報を共有できる機能があります。
共働き家庭や子育て世代では、「家族全体で支出を把握・調整」できることが大きな強みになります。
家計簿アプリのデメリット
操作に慣れるまで時間がかかる
アプリは便利な反面、機能が多すぎて「何から使えばいいの?」と戸惑うこともあります。
特に、初期設定(銀行口座やクレジットカードの連携)にハードルを感じる人も多く、慣れるまでが少し大変という点が挫折の原因になることも。
デジタルに依存する不安がある
家計簿アプリはスマホやクラウドに依存しているため、
- 機種変更時のデータ移行
- スマホ紛失・故障時のリスク
- アプリサービス終了時のデータ損失
といった技術的なトラブルや不安がつきものです。
バックアップ機能やデータのエクスポート機能を活用することが重要です。
セキュリティ面が気になる人には不向き
銀行口座やクレジットカードを連携することで、便利にはなるものの、「金融情報をアプリに預けるのは不安」という人にとっては心理的なハードルがあります。
セキュリティ対策が整っているアプリを選び、自分の感覚に合うかどうかを見極めることが大切です。
自動化による“無関心”のリスク
便利になりすぎると、逆に「お金の流れを把握する感覚が薄れる」ことがあります。
家計簿をただ見るだけで終わり、無意識にお金を使い続けてしまうようでは、本来の意味をなさなくなります。
“自動記録+手動の見直し”のバランスを取ることが重要です。
効率重視ならアプリ、でも意識化の習慣も大切に
家計簿アプリは、「家計簿は苦手」「手書きは続かない」「時間がない」人にとって、非常に頼れるツールです。
スマホ1つで家計の管理が自動化され、視覚的にもわかりやすく、忙しい人の味方になります。
ただし、「楽すぎるがゆえに、お金に無関心になってしまう」リスクもあるため、時々は振り返りの時間を持ち、自分の支出に意識を向けることが成功のカギです。
- 最初は無料プランで試してみる
- 連携せず手動入力から始める
- 週1回、支出をグラフで見返す
など、自分に合った“ゆるいスタート”で十分です。
アプリはあくまで「管理を助けてくれる道具」として、上手に活用していきましょう。
こちらもCHECK
-

-
無料で使える家計簿アプリおすすめランキング!初心者が使いやすい人気アプリまとめ
家計管理を始めたいけれど、「家計簿ってなんだか面倒そう…」「続けられるか不安…」という方も多いのではないでしょうか。 そんな方にぴったりなのが、スマホで手軽に使える無料の家計簿アプリです。 最近の家計 ...
続きを見る
あなたはどっち向き?タイプ別おすすめ診断

手書き家計簿がおすすめな人
家計簿は、「どちらが優れているか」で選ぶよりも、「自分に合っているかどうか」で選ぶのがポイントです。
性格や生活スタイル、家計への関心の高さなどによって、無理なく続けられる方法は人それぞれ異なります。
ここでは、手書きとアプリ、それぞれの家計簿がどんなタイプの人に向いているかを具体的に紹介します。
まずは、手書き家計簿が向いている人の特徴から見ていきましょう。
- 書くことが好き、または習慣になっている
- スマホやアプリ操作に抵抗がある
- 視覚的に「自分でまとめる」作業が向いている
- アナログで管理することで実感を得たい
家計簿アプリがおすすめな人
一方で、「記録する手間をなるべく減らしたい」「スマホを日常的に使っている」という人には、家計簿アプリの方がぐっとハードルが下がります。
特に忙しい毎日を送っている方や、クレジットカード・キャッシュレス決済を多く利用している人にとっては、自動で記録される便利さは非常に魅力的です。
ここでは、どんな人がアプリ家計簿に向いているかを具体的に紹介します。
自分のライフスタイルと照らし合わせながらチェックしてみてください。
- 毎日の記録が面倒に感じる
- クレジットカードや電子マネーを多用している
- 分析やグラフを見ながら改善したい
- スマホを日常的に活用している
「ハイブリッド型」もおすすめ
手書きとアプリの“いいとこ取り”をした「ハイブリッド型」も、続けやすいスタイルのひとつです。
- 日々の細かい支出はアプリで自動記録
- 月末にアプリの内容をノートにまとめて「振り返り」だけ手書きで
こんな感じで、「記録はアプリ、意識づけは手書き」と役割を分けることで、管理の効率と実感のバランスが取れます。
続けられる方法が“正解”
手書きもアプリも、それぞれにメリット・デメリットがありますが、一番大切なのは“自分が無理なく続けられるかどうか”です。
どちらを選んでも、「家計の流れを把握して、見直す習慣がつく」ことがゴール。
完璧を求めすぎず、まずは「合っているかどうか」を試してみることから始めましょう。
あなたのライフスタイルにフィットした家計簿スタイルが、きっと見つかるはずです。

