家族の食費、気づけば毎月家計を圧迫する大きな出費になっていませんか?
特に4人家族となると、外食やまとめ買い、子どものおやつ代など、ちょっとした積み重ねが家計の負担につながりがちです。
最新の統計によると、4人家族の1か月の食費は約10万円前後とされ、工夫なしでは簡単に予算オーバーするのが現実です。
しかし、安心してください。
この記事では、4人家族の食費の平均額という基礎データをもとに、今日から実践できる「自宅での節約術」と「買い物での節約術」を徹底解説します。
読めば、節約をストレスなく続けるコツがきっと見つかります。
もくじ
- 1 4人家族の月の食費は?最新の政府統計をチェック
- 2 自宅での節約術
- 2.1 1. 家計簿で食費の現状を把握し、週単位で予算を決める
- 2.2 2. 安い食材でできる定番メニューを複数用意しておく(例:鶏むね肉、豆腐、もやし、卵など)
- 2.3 3. 普段使わない調味料を使用する料理はしない
- 2.4 4. 冷凍保存・作り置きを活用し、食材を無駄なく使い切る
- 2.5 5. 肉・魚を小分け冷凍し、計画的に使う
- 2.6 6. お菓子すらも自分で作る
- 2.7 7. 飲み物は水と麦茶で十分、コーヒーやお茶は自分で淹れる
- 2.8 8. 節約レシピはネット上で簡単に見つかる
- 2.9 9. 余ったごはんは冷凍し、常備する
- 2.10 10. 家庭菜園・ベランダ菜園で簡単な野菜を育てる
- 2.11 11. 安売り調味料・長期保存品はまとめ買いし、ストック管理する
- 3 買い物での節約術
- 4 家族の食費節約は、小さな積み重ねが大きな効果に
4人家族の月の食費は?最新の政府統計をチェック
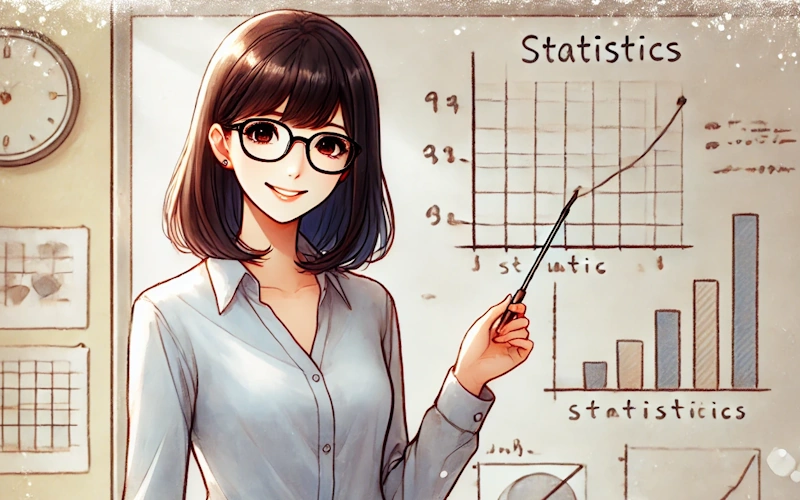
総務省統計局が実施している「家計調査」によると、2023年の二人以上の世帯における1か月あたりの食費(「食料」費目)は、全国平均で約76,000円となっています。
ただし、このデータは世帯人数によって異なります。4人家族の場合、以下のような傾向が見られます。
- 食費の増加:世帯人数が増えると、当然ながら食費も増加します。
- 一人当たりの食費の減少:一方で、食材のまとめ買いや調理の効率化により、一人当たりの食費は減少する傾向があります。
具体的な数値としては、4人家族の月間食費は約100,000円前後と推定されます。
これは、地域や生活スタイル、外食の頻度などによって変動します。
食費の内訳(参考)
家計調査では、食費の内訳も公表されています。主な項目は以下の通りです。
- 穀類:米やパン、麺類など
- 魚介類:魚や貝類など
- 肉類:牛肉、豚肉、鶏肉など
- 乳卵類:牛乳、チーズ、卵など
- 野菜・海藻:野菜全般、海藻類など
- 果物:りんご、バナナなど
- 油脂・調味料:食用油、醤油、味噌など
- 菓子類:和菓子、洋菓子など
- 外食:レストラン、ファストフードなど
これらの項目ごとの支出割合は、家族構成や食生活のスタイルによって異なります。
地域差と物価の影響
食費には地域差があり、都市部では物価が高いため食費も高くなる傾向があります。
また、外食の頻度や利用する店舗の価格帯によっても食費は変動します。
まとめます。
- 4人家族の月間食費:約100,000円前後(地域や生活スタイルにより変動)
- 食費の内訳:穀類、魚介類、肉類、乳卵類、野菜・海藻、果物、油脂・調味料、菓子類、外食など
- 地域差:都市部では食費が高くなる傾向
詳細なデータや最新の統計情報については、総務省統計局の「家計調査」ページをご参照ください。
自宅での節約術
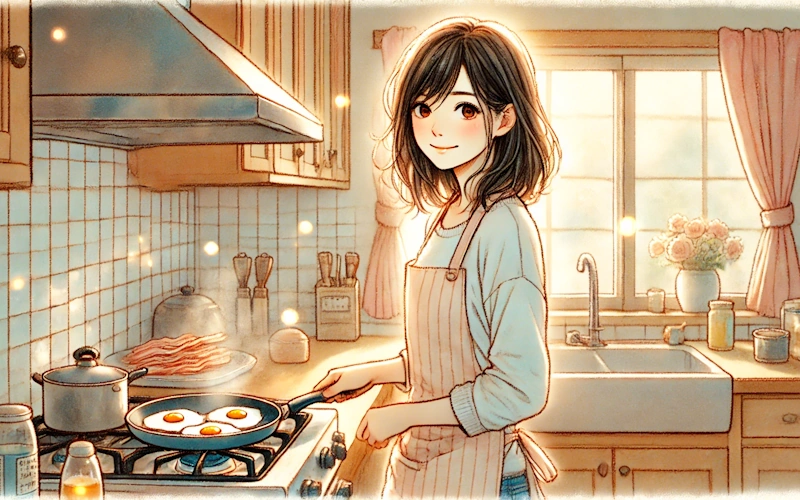
食費に関する節約術は、物価高騰に対して月の予算を上げたくない場合、必ず役に立つ知識です。
基本的なことが多くなりますが、ポピュラーな節約術をご紹介します。
1. 家計簿で食費の現状を把握し、週単位で予算を決める

節約を始めるうえで、まず最初に取り組みたいのは「現状の見える化」です。
特に食費は、無意識に支出が増えやすい項目です。外食、コンビニ、スーパーでのちょい買い…。
これらの積み重ねで、気づかぬうちに予算をオーバーしてしまいます。
家計簿をつけることで、1か月に自分や家族がどれだけ食費を使っているのかが明確になります。
最近はスマホアプリの家計簿が多く、レシート撮影や連携機能で自動入力できるものもあるので、記録のハードルはかなり下がっています。
家計簿をつけたら次のステップは「週単位の予算決め」です。
たとえば「1か月の食費予算が8万円」の場合、週単位に直すと約2万円。
この予算内でやりくりするクセをつけると、月末の予算オーバーを防ぎやすくなります。
週単位の管理は「今週は残りあと〇〇円」と進捗を確認しやすく、調整もききやすいのが大きな利点です。
こちらもCHECK
-

-
家計簿の付け方!初心者や苦手な人でも簡単に続けられるコツと方法
家計簿を付けることは、家計管理の基本であり、将来の安心や目標達成につながる大切な習慣です。 毎月の収入と支出を見える化することで、自分の「お金の使い方のクセ」がはっきりとわかり、無駄遣いや使いすぎを防 ...
続きを見る
2. 安い食材でできる定番メニューを複数用意しておく(例:鶏むね肉、豆腐、もやし、卵など)
節約料理の心強い味方が「安くて栄養価の高い食材」です。
鶏むね肉、豆腐、もやし、卵はその代表格で、どのスーパーでも比較的安定した低価格で手に入ります。
例えば、鶏むね肉は煮物、炒め物、サラダ、スープとアレンジの幅が広く、ボリュームも満点。
豆腐は麻婆豆腐、冷奴、味噌汁の具などに使え、もやしは炒め物、ナムル、味噌汁に重宝します。
卵は目玉焼き、卵焼き、オムレツ、丼物など、まさに万能食材です。
節約のコツは、これらの食材を使った「家の定番メニュー」をいくつか決めておくこと。
たとえば、
- 鶏むね肉の照り焼き丼
- 豆腐とひき肉のそぼろ煮
- もやしとニラの炒め物
- 卵のオムライス
こうしたメニューを固定化しておくと、買い物の際に迷わず必要なものを買え、無駄な食材購入が減ります。
毎日の献立づくりに悩む時間も減り、時間とお金のダブル節約につながります。
こちらもCHECK
-

-
【2025年度版】節約料理に欠かせない食材10選まとめ
2025年現在、日本の家庭を取り巻く食費の環境は大きく変わりつつあります。 食品の値上がりが続く中、無理なく節約しながらも、健康的で満足感のある食事を作るには、食材選びの工夫が欠かせません。 節約とい ...
続きを見る
3. 普段使わない調味料を使用する料理はしない
おしゃれなレシピやSNS映えする料理を作ろうとすると、つい「特別な調味料」を買いたくなるものです。
例えば、ナンプラー、オイスターソース、クミン、バルサミコ酢…。
普段の和食・洋食ではあまり出番がない調味料は、使い切れずに冷蔵庫の奥で眠り、最終的には捨てる羽目になることが多いです。
節約を意識するなら、まずは家にある基本の調味料(醤油、みりん、酒、砂糖、塩、酢、味噌、ソース、ケチャップなど)だけで作れる料理に限定しましょう。
「調味料の多さ=料理上手」ではなく、むしろ限られた調味料でおいしい料理を作れる人の方が、節約上手で賢いといえます。
もし新しい味に挑戦したい場合は、まず少量パックを試す、または代用できる調味料を調べるなどして、無駄買いを防ぎましょう。
4. 冷凍保存・作り置きを活用し、食材を無駄なく使い切る
食材のロスは、家庭の食費を圧迫する大きな原因のひとつです。
買った野菜が使い切れずに腐ってしまったり、まとめ買いした肉が消費期限を過ぎて廃棄されたり…。
こうした「もったいない」を防ぐには、冷凍保存と作り置きが有効です。
たとえば、
- 鶏むね肉やひき肉は小分けにして冷凍。
- 野菜は切って冷凍、キノコはほぐして冷凍。
パンやごはんも冷凍保存することで、買い足しの頻度を減らせます。
さらに時間に余裕があるときに作り置きをしておくと、忙しい日の外食やテイクアウトの誘惑を防げます。
煮物、カレー、ミートソース、肉団子などは作り置き向きで、冷蔵・冷凍どちらでも保存可能です。
保存の際は、ラップやジップロック、冷凍保存用バッグを使って、乾燥・酸化を防ぐことも忘れずに。
こうした工夫を重ねると、「使い切れなかった食材を捨てる」というストレスが減り、心理的な満足感も得られます。
5. 肉・魚を小分け冷凍し、計画的に使う
肉や魚は家庭の食費における“高額ゾーン”です。
まとめ買いで安く手に入れても、うっかり冷蔵庫で腐らせてしまえば元も子もありません。
ここで重要なのが「小分け冷凍」です。
例えば、特売で買った鶏むね肉や豚こま切れ肉を1食分ずつラップで包み、ジッパーバッグに入れて冷凍。
魚も同様に切り身を1切れずつ包んで冷凍します。
小分けしておくことで、使うときに必要な分だけ解凍でき、無駄に解凍して傷ませるリスクが減ります。
また、「次の献立」をイメージして冷凍すれば、計画的な食材消費が可能になります。
さらに、冷凍保存は食品の劣化を防ぐだけでなく、外食や中食(惣菜・弁当)の誘惑を減らす効果もあります。
忙しい日の夕飯や弁当作りでも、解凍して焼くだけ、煮るだけ、炒めるだけで済む材料があれば、節約と時短の一石二鳥です。
6. お菓子すらも自分で作る
お菓子代は、気づかぬうちに家計を圧迫する“隠れ食費”です。コンビニやスーパーでのおやつ代は、1回あたり数百円でも、週に何度も買えば月に数千円にのぼります。
ここでおすすめなのが「お菓子の手作り」です。
ホットケーキミックスで作る蒸しパンやカップケーキ、手作りクッキー、ゼラチンを使ったゼリーなどは、安価な材料で大量に作れます。
特に子どもがいる家庭では、一緒に作ることで親子のコミュニケーションにもなり、市販のお菓子に頼らない習慣が自然と身につきます。
もちろん、手作りお菓子の最大のメリットは「量とコスパ」。市販の個包装お菓子は便利ですが、1個あたりの価格は意外と割高です。
自宅で作れば、1回分の材料費で数回分のおやつがまかなえ、節約と満足感を両立できます。
7. 飲み物は水と麦茶で十分、コーヒーやお茶は自分で淹れる
飲み物代も節約の大きな狙い目です。
毎日ペットボトル飲料を買うと、1本150円としても1か月約4,500円。
家族全員が買えば、4人家族なら単純計算で月1万8,000円。これはかなりの支出です。
まず、日常の飲み物は基本「水と麦茶」で十分と割り切ります。
水道水を使った冷水ポットの麦茶は、夏場の水分補給に最適。
さらにコーヒーやお茶は自宅で淹れる習慣をつけましょう。
ドリップコーヒー、紅茶、緑茶をマイボトルに入れて持ち歩けば、外出時の飲料代がゼロになります。
特にオフィス勤務の方は、「コンビニでコーヒーを買うのが習慣」という方も多いですが、これをやめるだけで1か月で数千円が浮きます。
麦茶や水、マイボトルコーヒー生活は、節約だけでなくエコにもつながるため、罪悪感ゼロの良習慣です。
8. 節約レシピはネット上で簡単に見つかる
「節約料理」と聞くと、料理本を買わなきゃ、雑誌をチェックしなきゃ…と思うかもしれませんが、今はその必要はありません。
ネット上には、無料で見られる節約レシピが大量にあります。
例えば、クックパッド、楽天レシピ、クラシル、DELISH KITCHENといった大手レシピサイトや、YouTubeの料理チャンネルには、材料費を抑えた簡単メニューが山のように投稿されています。
特に「○○ 円レシピ」「1人前 100円レシピ」などのキーワードで検索すれば、驚くほどバリエーション豊かな料理が見つかります。
この情報の豊富さを使わない手はありません。
一度「我が家の定番節約レシピリスト」を作っておくと、献立を決めるスピードが格段に上がり、節約生活が続けやすくなります。
調理動画なら手順もわかりやすく、料理が苦手な方でも挑戦しやすい点も大きなメリットです。
9. 余ったごはんは冷凍し、常備する
家庭の食費節約で見落とされがちなのが「炊いたごはんの管理」です。
つい多めに炊いてしまい、食べきれずに冷蔵庫で放置、数日後にカピカピに…という経験は誰にでもあるのではないでしょうか。
余ったごはんは、早めに冷凍保存するのが鉄則です。
炊きたてのうちに茶碗1杯分ずつラップで包み、粗熱が取れたら冷凍庫へ。平たく包むと解凍も早く済みます。
これにより、無駄を防ぐだけでなく、忙しい日の強い味方にもなります。
たとえば「ごはんさえあれば、卵かけごはんやチャーハン、雑炊ですぐ1食完成」という安心感があるので、外食やテイクアウトに走るリスクも下がります。
冷凍ごはんは1か月程度保存可能とされますが、風味が落ちないうちに食べきるのがおすすめです。
冷凍庫の中に「安心の主食ストック」があると、家計管理にも心理的にも大きな余裕が生まれます。
10. 家庭菜園・ベランダ菜園で簡単な野菜を育てる
節約の中・上級者にぜひ挑戦してほしいのが、家庭菜園やベランダ菜園です。
大げさな農業は必要ありません。まずはミニトマト、ピーマン、バジル、しそ、ネギなど、簡単に育つものから始めましょう。
最近では、100円ショップやホームセンターで手軽に栽培セットが手に入ります。
特にミニトマトはプランターと苗があればOKで、初心者向けの野菜の定番。夏場は次々と実をつけ、毎日のお弁当やサラダに大活躍します。
また、使いかけのネギの根元を水につけて再生栽培する、豆苗を根元から育て直すといった「リボベジ」もおすすめです。
家庭菜園の良い点は、食費節約だけでなく、家族で楽しめるイベントになること。
特に小さいお子さんがいる家庭では、野菜ができる過程を一緒に観察することで、食育にもつながります。
収穫の喜びを味わいながら、家計にもやさしい—まさに一石二鳥です。
11. 安売り調味料・長期保存品はまとめ買いし、ストック管理する
調味料や長期保存がきく食材は、安売りのときにまとめ買いしておくと非常にお得です。
たとえば、砂糖、塩、みそ、しょうゆ、油、缶詰、乾麺、冷凍食品、レトルト食品などは、まとめ買いの対象として優秀。
通常価格で1本400円のしょうゆが、特売日なら300円以下になることも珍しくありません。
ただし、まとめ買いには注意点もあります。
- 賞味期限を確認し、使い切れる分だけ買う
- 在庫管理をきちんと行い、二重買いや買いすぎを防ぐ
- 収納スペースを確保しておく
調味料の在庫が増えると、かえって何があるのかわからなくなることがあります。
そこで、冷蔵庫や食品棚の中を定期的に整理し、残量チェックや使いかけ品の確認を習慣化しましょう。
ストック管理がしっかりできれば、いざというときの「買い物しなくていい日」を作れ、さらに節約効果が高まります。
買い物での節約術

1. 食品(肉・魚・野菜)はチラシ・アプリを必ずチェック
食費を抑えるうえで、もっとも即効性があるのが「買う前の情報収集」です。
スーパーのチラシやアプリには、毎週お買い得な特売品情報が載っています。
特に、肉・魚・野菜といった生鮮品は日替わり・週替わりで大きく価格が変動するため、チラシやアプリをチェックするかどうかで、同じ買い物でも数百~数千円の差がつくことがあります。
最近ではアプリを入れるだけで、近隣店舗のチラシが一括で見られるサービスも登場しています。
「買い物のついでに安い商品を探す」のではなく、
「安いものを決めてから買い物に行く」
という意識に切り替えるだけで、食費節約の効率は大きく変わります。
2. 肉や魚は安い日にまとめ買いして冷凍する
肉や魚は家庭の食費のなかで割合が大きい食材です。
特売日を狙ってまとめ買いし、小分け冷凍するのが鉄則です。
例えば、スーパーによっては「毎週火曜はお肉の日」「水曜は魚の特売日」といった独自の安売り日があります。
そのタイミングで、鶏むね肉や豚こま、魚の切り身をまとめ買いし、帰宅後に1食分ずつラップに包み、ジッパーバッグに入れて冷凍庫へ。
使うときに必要分だけ解凍できるので、食品ロスも減らせます。
この方法を続けると、通常価格で少しずつ買うより1~2割、場合によっては半額近い節約効果が出ることがあります。
特売日に合わせて献立を考えるクセをつけると、さらに効果的です。
3. 圧倒的に安い外国産の肉を買う
食材の選び方そのものを見直すのも、節約の重要なポイントです。
特に肉類では、国産にこだわらず外国産を選ぶだけで、価格は大きく変わります。
例えば、鶏むね肉なら国産100gあたり約80~120円ですが、外国産なら60~80円程度。
豚バラなんて、国産100gあたり250円~300円に対し、外国産は150~200円程度で購入可能です。
牛肉や他の豚肉も同様で、外国産は国産の約7割以下の値段で売られていることが多いです。
外国産の肉は「硬い・臭みがある」というイメージがあるかもしれませんが、下味冷凍や漬け込み調理を活用すれば、柔らかく臭みのない仕上がりになります。
特にとんかつ用のロース、生姜焼き用の薄いロースなどは、外国産であれば安い時は100gあたり100円以下で購入できる場合もあるので、かなりお得です。
節約だけでなく、料理の幅も広げるチャンスだと考えると、取り入れやすくなるでしょう。
こちらもCHECK
-

-
節約派必見!外国産の安い豚肉・鶏肉・牛肉はなぜお得?特徴と価格、安全性まとめ
家計を支える上で「お肉」は欠かせない食材のひとつですが、最近では物価上昇が続き、国産肉はなかなか手が出しづらいという声も増えています。 そんな中、スーパーでは外国産の安価な肉が目立つようになり、 「値 ...
続きを見る
4. 野菜が安い店・肉が安い店の傾向を把握しておく
買い物上手になるためには、近所のお店の「得意分野」を知っておくことが重要です。
たとえば、
- Aスーパー → 野菜が安い
- Bスーパー → 肉が安い
- Cスーパー → お米や冷凍食品が安い
このような店ごとの特徴を把握しておくと、必要なものに応じて店を使い分けられます。
最近ではドラッグストアが生鮮品を扱うケースも増えており、「ドラッグストアの方が牛乳が安い」といった逆転現象も珍しくありません。
最初はメモやスマホで価格の比較表を作ってもOKですし、家族で情報をシェアするのも手。
慣れてくると「今日は肉が必要だからBスーパー、野菜はAスーパーで買おう」という判断がスムーズになり、ムダ買いや高値づかみを防げます。
5. 外食はもちろん、コンビニ利用も控える
節約の王道といえば「外食を減らす」ですが、意外と見落とされがちなのがコンビニ利用です。
外食を控えていても、「ちょっと小腹が空いたから」「飲み物を1本だけ」とコンビニに寄ってしまうと、1回あたりの出費は少額でも月トータルでは大きな負担になります。
例えば、コンビニでのちょっとした買い物が1回あたり500円だとしても、週3回利用すれば月約6,000円。家族全員がそれを続ければ、月2~3万円になることも。
スーパーでまとめ買いをして、家にストックを作っておくことで、外出先での無駄な買い物を防げます。
また、マイボトルやおやつの持参も効果的です。
「コンビニは急ぎのときだけ」というルールを決め、できるだけ立ち寄らないように心がけましょう。
6. 割引の時間帯(見切り品)をしっかり把握しておく
スーパーでは、閉店前の夕方や夜に割引シールが貼られることが多いです。
これを狙って買い物をするのは、節約上級者の定番テクニックです。
具体的には、
- 魚売り場:17時ごろ
- 肉売り場:18時ごろ
- 惣菜・弁当コーナー:19時以降
といった時間帯に値引きが始まる店舗が多く、半額商品を手に入れられることもあります。
ただし注意点として、「割引だからといって不要なものまで買わない」「割引品を狙いすぎて過剰なまとめ買いをしない」ということが大切です。
見切り品を効率よく取り入れるには、あらかじめ購入リストを決め、「安ければ買う」というスタンスに留めるのがコツです。
因みに、お店によっては朝一番で見切り品を半額に下げるところもありますので、狙い目です。
7. 買い物は短時間・1人で済ませ、余計な買い物を避ける
スーパーに長居すると、つい予定外の商品が目に入ってしまいます。
「特売のチョコレートが安い」「新発売のジュースが気になる」といった衝動買いは、短時間の買い物なら回避しやすくなります。
また、家族全員で行くと、子どもに「これ買って!」とせがまれたり、予定外の商品をカゴに入れたりして、結果的に出費が増えることが少なくありません。
節約を意識するなら、買い物はできるだけ1人で、かつ短時間で済ませるのが賢明です。
買い物前にメモを用意し、必要なものだけを買う「ミッション方式」で臨むと、無駄遣いを防ぎやすくなります。
8. 子供のお菓子は駄菓子を選ばせるのが吉
子どものお菓子代も、家計にじわじわ響いてくる支出です。
コンビニやスーパーのスナック菓子は1袋150~200円程度。
小さい子が2~3個欲しがれば、あっという間に500円超えです。
そこでおすすめなのが「駄菓子屋感覚」での買い物です。
スーパーやドラッグストアの駄菓子コーナーには、10円~50円の小さなお菓子が豊富にあります。
「好きなのを〇個選んでいいよ」というルールにすれば、子どもは選ぶ楽しみを味わえ、親は出費をコントロールできます。
また、子どもに「お菓子の予算」をあらかじめ伝えておくと、お金の価値を学ぶ良いきっかけにもなります。
節約は家族全員で楽しむもの、というスタンスを作るのも効果的です。
家族の食費節約は、小さな積み重ねが大きな効果に
4人家族の平均的な食費は、決して少なくない金額です。
でも、今回ご紹介した自宅・買い物での節約術を少しずつ取り入れるだけで、毎月数千円、年間では数万円の節約が実現できます。
家計簿での見える化、冷凍保存の活用、特売日のまとめ買い、コンビニの回避、子どもとの駄菓子ルール…。
こうした「できることから一歩ずつ」が、ストレスのない家計管理につながります。
家族で楽しみながら節約に取り組み、浮いたお金をレジャーや将来のための貯蓄に回す。
そんな前向きな節約ライフを、ぜひ今日から始めてみてください。

