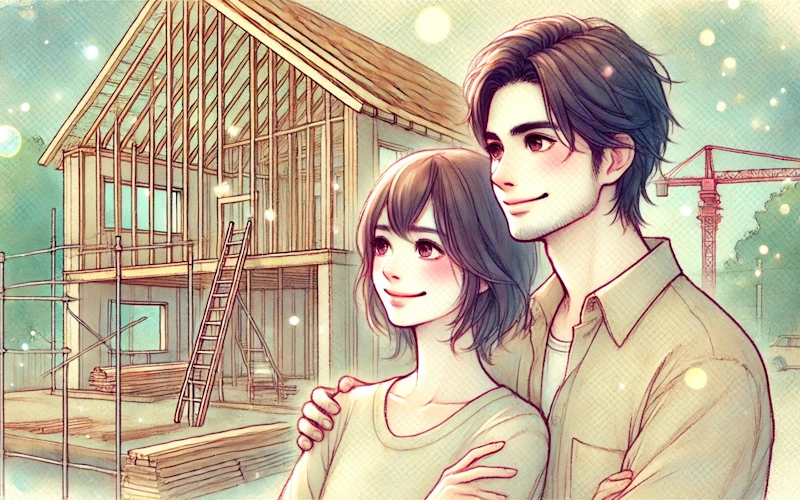住宅の購入やリフォームを検討する際、少しでも費用を抑えたいと考える方は多いはずです。
実は、国や自治体では、住まいづくりにかかる費用の一部を支援するために、さまざまな補助金や助成金制度を設けています。
制度を上手に活用すれば、数十万円〜数百万円規模の支援を受けられることも珍しくありません。
ただし、補助制度は種類が多く、それぞれに対象条件や申請方法が異なるため、「自分が使える制度がわからない」「申請方法が難しそう」と感じてしまう人も少なくないのが現実です。
そこで本記事では、2025年時点で利用可能な住宅関連の補助金・助成金制度を網羅的にご紹介します。
新築・中古購入、リフォーム、空き家活用、移住支援まで、幅広い目的に対応した制度を丁寧にまとめていますので、ご自身のケースに合った支援策を見つける参考にしてください。
もくじ
住宅購入・リフォームで使える補助金&助成金まとめ
1. こどもエコすまい支援事業
こどもエコすまい支援事業は、子育て世帯や若者夫婦世帯が高性能な省エネ住宅を取得する際に活用できる補助金制度です。
2025年度も継続が見込まれており、対象となる住宅を購入または新築する場合、条件を満たせば最大100万円の補助が受けられます。
この制度の特徴は、子育て支援と住宅の省エネ化を同時に推進している点です。
補助の対象となるのは、長期優良住宅やZEH水準の新築住宅など、一定の基準を満たす高性能住宅に限られており、環境性能と居住性の両立が求められます。
補助金の申請は、必ず「登録事業者」を通じて行う必要があり、個人が直接申請することはできません。
工事や契約のタイミングも制度で定められているため、早めに対応を始め、対象となる事業者と計画を立てておくことが重要です。
子育て世帯や住宅購入を検討中の若年層にとって、住宅取得費の負担を大きく軽減できる制度として、見逃せない支援策となっています。
2. 子育てエコホーム支援事業
子育てエコホーム支援事業は、省エネ性能の高い新築住宅やリフォームに対して補助金が支給される国の制度です。
こどもエコすまい支援事業の後継的な位置づけとなっており、2025年も継続される見込みです。
新築については、子育て世帯または若者夫婦世帯が、一定の省エネ基準を満たす住宅を建築・購入する場合に対象となり、最大100万円の補助が受けられます。
リフォームの場合は、年齢や家族構成を問わず、すべての世帯が対象となり、内容に応じて最大60万円程度までの補助が用意されています。
対象となる工事は、断熱改修、エコ住宅設備の設置、バリアフリー改修など多岐にわたり、複数のメニューを組み合わせて補助額を積み上げることも可能です。
申請は登録事業者を通じて行うため、事前に対象工事かどうかの確認を行い、申請書類の準備とスケジュールの調整が必要です。
家族のライフステージや住宅の老朽化に応じたリフォーム計画にも対応できる、柔軟で実用的な支援制度となっています。
3. 先進的窓リノベ事業
先進的窓リノベ事業は、住宅の窓を断熱性の高い製品に交換することで、省エネ性能の向上と冷暖房費の削減を促進する補助金制度です。
2025年も実施予定で、特にエネルギーコストの上昇が続く中、注目度が高まっています。
この制度の魅力は、補助額の大きさと対象範囲の広さです。
補助金は1戸あたり最大200万円に達することもあり、窓のサイズや工事内容に応じて単価が設定されています。
対象となるのは、内窓設置・外窓交換・ガラス交換などで、一定の断熱性能基準を満たす製品の使用が条件です。
補助対象は戸建住宅だけでなく、マンションの専有部分も含まれており、すべての世帯が申請可能です。
申請手続きは登録事業者が行うため、事前に見積もりや工事計画を立てることが必要です。
快適性の向上に加えて、冬の結露防止や夏の冷房効率アップなど、長期的な住環境改善につながる実用的な補助制度として活用が進んでいます。
4. 給湯省エネ事業
給湯省エネ事業は、高効率の給湯設備を導入する家庭に対して、設置費用の一部を補助する制度です。
脱炭素化とエネルギーコスト削減を目的としており、エコキュートやハイブリッド給湯器、エネファームなどが主な対象機器となります。
2025年度も継続予定で、1台あたりの補助金額は5万円〜13万円程度となっており、機種や性能によって異なります。
複数台設置する場合や、蓄熱機能付きの機器には加算が設定されているケースもあります。
対象となるのはすべての世帯であり、新築・既築を問わず申請可能です。
申請は登録された住宅関連事業者が代行し、補助額分を差し引いた形で契約することもできます。
申請から支給までの期間が比較的短いため、急な故障による交換でも利用しやすい制度となっています。
光熱費を抑えつつ、環境にやさしい暮らしを実現したい家庭にとって、導入のハードルを下げてくれる実用的な支援策です。
5. 長期優良住宅化リフォーム推進事業
長期優良住宅化リフォーム推進事業は、既存住宅の性能向上を目的として、国土交通省が実施している補助金制度です。
対象となるのは、耐震性・省エネ性・劣化対策・バリアフリー性などの各性能をバランスよく高めるリフォームで、2025年度も引き続き実施される予定です。
この制度では、工事内容や住宅の状況に応じて、最大250万円までの補助が受けられます。
特に「高度省エネ型」「高度省エネ・耐震型」など、より高性能なリフォームを行う場合は補助額も増額されます。
また、インスペクション(住宅診断)の実施や、リフォーム履歴・維持保全計画の作成も要件に含まれており、住宅の長寿命化が前提となっています。
補助を受けるには、事業に対応したリフォーム事業者を通じて申請する必要があり、個人申請はできません。
計画段階からの事前審査が必要となるため、早めに準備を進めることが大切です。
住宅の資産価値を高めながら、安全で快適な住環境を長く保ちたい方にとって、非常に有効な支援制度といえるでしょう。
6. ZEH支援事業(ZEH補助金)
ZEH支援事業(ネット・ゼロ・エネルギー・ハウス支援事業)は、省エネ性と創エネ性能を備えた住宅「ZEH(ゼッチ)」の建築や購入を促進するために設けられた補助金制度です。
2025年も継続される見込みで、脱炭素社会の実現に向けた中核施策の一つとされています。
ZEH住宅は、高断熱・高効率の設備でエネルギー消費を最小限に抑えた上で、太陽光発電などにより消費エネルギーの全量以上を創出する住宅です。
この基準を満たす住宅を建築または購入する場合、1戸あたり55万円〜最大100万円程度の補助が受けられます。
条件を満たせば、蓄電池の設置や寒冷地加算などによる追加補助も可能です。
申請は「ZEHビルダー」として登録された事業者を通じて行う形式で、契約や着工前の事前申請が必須です。
工事完了後の申請は一切受け付けられないため、タイミングには十分な注意が必要です。
光熱費の削減、快適な住環境、高い資産価値という三拍子が揃ったZEH住宅は、これからの住まい選びのスタンダードとなる存在です。
補助金を活用することで、初期費用の負担を大きく抑えながら、先進的な暮らしを実現できます。
7. 自治体独自のリフォーム補助制度
国の制度とは別に、多くの都道府県・市区町村では、地域ごとの課題や住民ニーズに応じたリフォーム補助制度を独自に設けています。
内容は自治体ごとに大きく異なりますが、空き家対策、子育て支援、高齢者の住環境整備、防災強化などを目的とした支援が中心です。
主な例としては、以下のようなものがあります。
- バリアフリー改修に対する補助(例:手すり設置・段差解消など)
- 三世代同居・近居のための改修費補助
- 住宅の耐震改修に対する費用補助
- 空き家を活用する際のリフォーム支援
- 高齢者向け住宅改修助成(介護予防を目的とした住宅改善)
補助額は数万円〜数十万円程度が一般的で、自治体の予算に応じて内容や上限額が変動します。
多くは「工事前の申請が必須」「地域業者の利用が条件」「所得制限がある」などの細かい条件があります。
また、受付期間が短かったり、年度途中で予算に達して受付終了となるケースもあるため、希望する方は早めに自治体の住宅政策課や公式サイトで最新情報を確認し、計画的に申請を進めることが大切です。
こうした自治体のリフォーム支援は、国の補助制度と併用できる場合もあるため、上手に組み合わせることでさらに費用負担を軽減することが可能です。
8. 自治体の空き家改修補助制度
空き家の有効活用を促進する目的で、多くの自治体が「空き家改修補助制度」を導入しています。
これは、長年使われていない住宅を取得または賃借してリフォームする場合に、その改修費用の一部を補助する制度です。
人口減少対策や地域活性化を目的とした重要な支援策として位置づけられています。
補助対象となる工事は、住宅としての安全性や快適性を確保するために必要な改修全般で、水回りの更新、屋根や外壁の修繕、断熱性能の向上、耐震補強、バリアフリー化などが含まれます。
補助額は上限50万円〜100万円程度が一般的ですが、自治体によっては移住者や子育て世帯に加算を行っているところもあります。
また、対象物件が自治体の「空き家バンク」に登録されていることや、一定期間定住する意思があることなどが条件となることが多く、物件選定の段階から制度利用を前提とした計画が求められます。
工事前の申請が必須である点、自治体が指定する業者を利用する必要がある点など、細かいルールが設けられているため、制度を利用したい場合は早い段階で窓口に相談し、必要な準備を進めることが重要です。
9. 自治体の三世代同居・近居促進補助制度
三世代での同居や近居を支援する「三世代同居・近居促進補助制度」は、子育て支援や高齢者の見守り体制強化、地域コミュニティの活性化などを目的として、多くの自治体で導入が進んでいる住宅支援制度です。
この制度では、親世帯と子世帯、または祖父母・親・子の三世代が、1つの住宅で同居する、もしくは同一市区町村内または一定距離圏内に居住することを前提に、住宅の取得費や改修費用の一部が補助されます。
補助額は自治体によって異なりますが、20万円〜100万円程度が目安で、子育て世帯や移住者には上乗せ補助が適用されるケースもあります。
対象工事としては、玄関・水回りの増設、間取り変更、バリアフリー化、増築や耐震工事などが含まれ、事前に家族構成や住所、関係性を証明する必要があります。
さらに、補助対象の住宅に一定期間居住することや、同居・近居開始後の届け出なども求められる場合があります。
補助金の交付には事前申請が必要であり、審査期間が設けられているため、住宅購入やリフォームのスケジュールに余裕を持った計画が求められます。
家族の暮らしをより安心・快適なものにするための後押しとして、非常に実用的な制度です。
10. 自治体の住宅取得に対する利子補給制度(住宅ローン補助)
住宅取得時にかかる住宅ローンの利息負担を軽減するため、自治体によっては「利子補給制度(住宅ローン補助)」を設けている場合があります。
これは、一定の条件を満たす住宅ローンに対して、利子相当分を自治体が補助することで、実質的な月々の返済額を抑えることができる制度です。
対象となるのは、主に新築住宅の取得者、子育て世帯、若年層、またはUターン・Iターンによる移住者などで、自治体ごとに年齢制限や所得制限、居住年数の条件が定められていることがあります。
対象となるローンは、地方銀行や信用金庫など自治体と提携している金融機関からの融資に限られている場合もあります。
補助の内容は、利子の一部(例:年0.5%相当)を一定期間(多くは5年間)にわたって補助するという形式で、トータルで数万円〜十数万円の支援となるケースが一般的です。
申請には、ローン契約書や償還予定表、住民票、収入証明書などの提出が求められ、工事完了または入居後に申請するパターンと、事前審査が必要なパターンがあります。
この制度を活用することで、住宅購入後の長期的な家計負担を軽減し、将来設計をより安定したものにできるため、特に住宅取得が初めての方にとっては心強い支援制度です。
11. 自治体独自の住宅購入補助制度
多くの自治体では、地域内で住宅を購入する住民に対して、費用の一部を助成する「住宅購入補助制度」を独自に設けています。
これは、地域への定住を促すと同時に、若年層や子育て世帯の住宅取得を後押しすることを目的とした支援制度です。
対象となる住宅は、新築・中古ともに含まれる場合がありますが、購入後に一定期間継続して居住することが要件となるのが一般的です。
補助額は10万円〜50万円程度が中心で、自治体によっては家族構成や年齢、所得に応じて加算措置を設けているケースもあります。
また、環境性能や耐震性能を備えた住宅であることが条件とされる場合もあります。
申請には、売買契約書、登記事項証明書、住民票、所得証明書などが必要となり、補助金は申請後に一括支給される場合と、段階的に支給される場合があります。
補助を受けた後に転出した場合は返還義務が生じることもあるため、制度の詳細を事前に把握しておくことが重要です。
自治体によっては、住宅購入支援に加えて、引越費用や家具・家電購入費の補助をセットで行っていることもあり、複数の制度を組み合わせることで、初期費用を大きく抑えることが可能です。
12. 自治体の移住・定住促進住宅補助制度
地域の人口減少や空き家の増加に歯止めをかけるため、各地の自治体では「移住・定住促進住宅補助制度」を導入しています。
この制度は、都市部などからの移住者が、対象地域で住宅を取得または改修する際に、補助金を支給することで新たな定住を支援するものです。
主な対象者は、県外・市外からの移住者、Uターン・Iターン希望者、テレワーク等を活用した地方移住者などで、年齢制限や所得条件が設けられている場合もあります。
対象住宅は、新築・中古住宅の購入、あるいは空き家バンク登録物件の改修などが多く、物件選定や契約のタイミングにも制限があることが一般的です。
補助額は20万円〜100万円前後が主流で、子育て世帯・若年世帯・多世帯同居など、特定の条件を満たす場合は加算されるケースもあります。
あわせて就業支援や起業支援といった他の制度と連携している自治体もあり、移住希望者には非常に魅力的な支援内容となっています。
申請には、移住元・移住先の住民票、住宅契約書、定住誓約書などが必要で、原則として移住後に一定期間定住する義務が発生します。
申請タイミングや受付期間が限定されている自治体も多いため、事前のスケジュール調整と情報収集が欠かせません。
地域の新たな生活基盤を築くにあたって、移住・定住促進制度は大きな支えとなる制度です。
特に地方移住を検討している方は、自治体の公式サイトで最新情報を必ず確認しておきましょう。
知っているだけで大きな差が出る、住宅補助制度の活用を
住宅に関する補助金や助成金は、返済不要でありながら、申請しなければ受け取れない「申請型支援」です。
つまり、制度を「知っている人だけが得をする」仕組みとも言えます。
今回ご紹介したように、国の制度だけでなく、各自治体でも独自の支援策が数多く存在しており、うまく活用することで負担を大幅に軽減することが可能です。
住宅の取得やリフォームは、人生の中でも大きな買い物です。
だからこそ、少しでも有利な条件で進められるよう、制度の内容を早めに確認し、事前準備を怠らないことが成功のカギとなります。
なお、各制度は予算が限られており、受付終了が早まることや年度ごとの内容変更があることも珍しくありません。
必ず最新の情報を各自治体や省庁の公式サイトで確認し、わからない点があれば早めに窓口へ相談するようにしましょう。
この記事が、あなたの住まいづくりの選択肢を広げ、経済的な負担軽減につながる一助となれば幸いです。