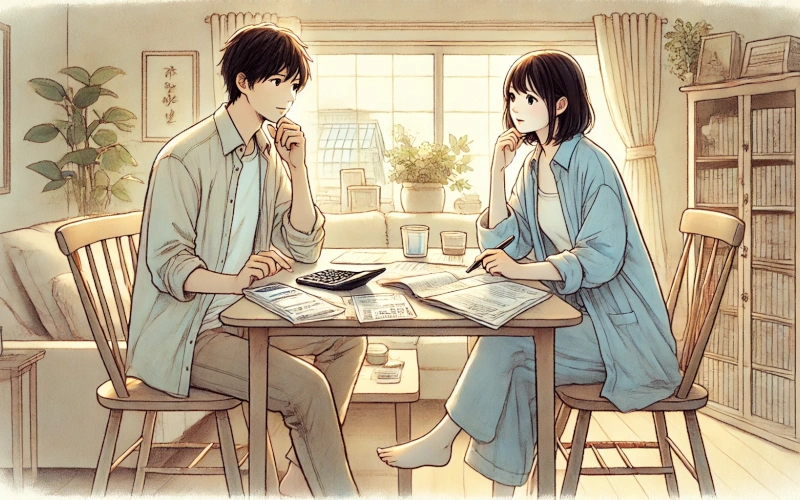共働き世帯が増える中で、よく話題に上がるのが「家計の分担、どうしてる?」という問題です。
お互いに収入があるからこそ、話し合いなしに済ませてしまうと、後々トラブルや不満の原因になることも。
この記事では、共働き家庭の家計管理について、初心者でもわかりやすく、分担方法の例やポイントを解説します。
もくじ
共働き家庭における家計管理の重要性

共働きの場合、「家計管理はどちらがどれだけ負担するか」「貯金は一緒にするのか個別にするのか」など、決めるべきことが意外と多くあります。
夫婦でお金の価値観が異なる場合、そのギャップがストレスの原因になることも。
だからこそ、早い段階で話し合い、ルールを決めることが重要です。
家計分担の主な方法とそのメリット・デメリット
共働き世帯では、お互いに収入があるからこそ、家計の分担方法に悩む家庭も多いものです。ここでは、実際によく使われている家計の分担方法を4つに分けて、それぞれの特徴とメリット・デメリットを詳しくご紹介します。
1. 収入に応じて割合で分担する
夫婦のそれぞれの収入額に応じて、家計の支出を負担する割合を決める方法です。
たとえば、夫が月収30万円、妻が20万円なら、6:4の割合で家計支出を分担します。
家賃、食費、水道光熱費など、すべての支出を合算したうえで、比率に基づいて負担する形です。
メリット
・収入差を考慮して負担できるため、お互いに無理がない
・公平性があり、パートナー間の不満が出にくい
・ボーナスなどの臨時収入にも比率を適用しやすい
デメリット
・毎月の支出合計を把握し、計算して割り振る必要がある
・正確にやろうとすると手間がかかり、細かい調整が面倒
・家計簿の共有や定期的な見直しがないと誤差が広がる
2. 固定費・変動費で役割を分ける
「家賃・光熱費など毎月ほぼ同じ金額がかかる支出(固定費)」と、「食費・日用品・交際費など月によって変動する支出(変動費)」を、それぞれどちらかが担当する方法です。
たとえば、夫が家賃・光熱費を支払い、妻が食費・日用品を負担するように分けます。
メリット
・「どちらが何を支払うか」が明確になり、管理しやすい
・支出項目ごとに責任が分かれるので役割分担の意識が持てる
・収支の変動を追いやすく、節約ポイントも見つけやすい
デメリット
・家計の支出に偏りが出ると、不公平感が生まれやすい
・物価の変動やライフスタイルの変化で負担バランスが崩れやすい
・「相手が払っている金額」を把握しづらく、透明性に欠ける場合も
3. 口座を一つにまとめて共有財布方式
共通の銀行口座や電子マネー口座を用意し、そこにふたりの収入の一部または全額を入れて、生活費や貯金などをすべて一本化して管理するスタイルです。
収入に差があっても、「ふたりのお金」として一括で扱います。
メリット
・家計の全体像を把握しやすく、将来設計や貯金計画が立てやすい
・すべての支出が1つの口座で管理できるので、透明性が高い
・家計簿アプリなどとの相性が良く、効率的に運用できる
デメリット
・お小遣いの境界があいまいになりやすく、使い方に不満が出ることも
・「自由に使えるお金がない」と感じる人にはストレスになりやすい
・どちらかが浪費すると家計全体に影響が出るリスクがある
4. 支出をざっくり折半する
支出の合計額をざっくり半分ずつにして負担する最もシンプルな方法です。たとえば、月に生活費が20万円かかるなら、各自10万円ずつ出し合うといった形です。金額の細かい内訳にとらわれず、毎月決まった金額を出すだけで済みます。
メリット
・とにかく簡単で、毎月の管理がしやすい
・アプリや家計簿が苦手な人でも始めやすい
・分担が明確なのでトラブルになりにくい(初期段階では)
デメリット
・収入に差がある場合は、負担感に差が出やすく不公平に感じることも
・支出の内訳があいまいなまま進むと、貯金や見直しが難しくなる
・貯金目標やライフプランに対する認識のズレが出やすい
おすすめのスタート方法は「ゆるく始める」
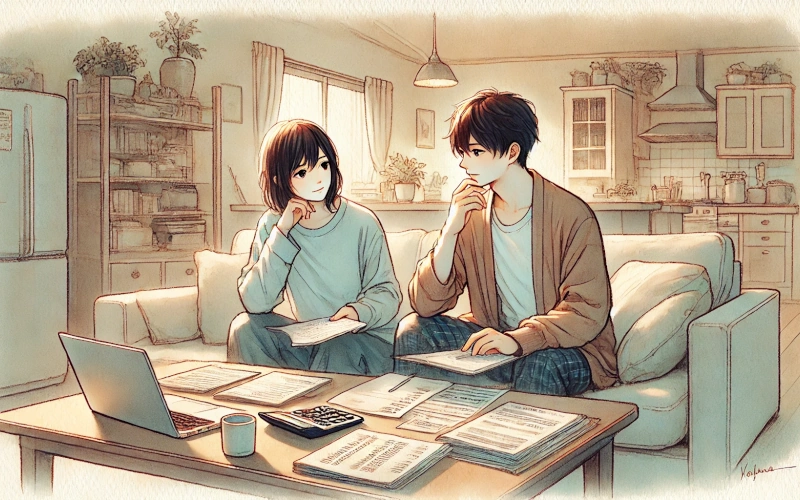
家計管理を始めるにあたって、いきなり完璧を目指してしまうと、途中で疲れて挫折しやすくなります。
特に共働き家庭は忙しく、家計の分担や記録のルールを細かく決めようとすると、話し合い自体がストレスになることもあります。
だからこそ、最初は「ゆるく・無理なく」スタートすることが何よりも大切です。
まずは「一つだけ」決めることから
最初から家賃、食費、水道光熱費、通信費、貯金額などすべてを細かく分担しようとせず、たとえば「家賃だけは夫が払う」「食費はふたりで月3万円ずつ出し合う」など、1つか2つのルールを決めるだけで十分です。
慣れてきたら、他の支出項目も見直していけばOK。
一気に整えようとせず、「今月はこの項目だけ考えよう」という姿勢が長続きのコツです。
支出の見える化は“ざっくり”でOK
最初から完璧な家計簿をつけようとせず、「今月は食費が多かったかも」「今週はコンビニに何回行ったかな?」という程度の“ざっくりした把握”でも大きな一歩です。
無料の家計簿アプリやスマホのメモ機能を活用すれば、支出の傾向をつかむだけでも十分な家計改善につながります。
こちらもCHECK
-

-
無料で使える家計簿アプリおすすめランキング!初心者が使いやすい人気アプリまとめ
家計管理を始めたいけれど、「家計簿ってなんだか面倒そう…」「続けられるか不安…」という方も多いのではないでしょうか。 そんな方にぴったりなのが、スマホで手軽に使える無料の家計簿アプリです。 最近の家計 ...
続きを見る
パートナーと「軽く話す習慣」を持つ
重たい話し合いではなく、「今月、スマホ代ちょっと高かったね」「ふたりで旅行用に毎月1万円貯めてみる?」といった、ライトな雑談レベルから始めてみるのがおすすめです。
定期的に“お金の話ができる空気”を作っておくことで、家計についての価値観をすり合わせやすくなり、
トラブルの予防にもなります。
まとめ
共働き家庭の家計管理は、パートナーとの信頼関係を築く上でも重要なテーマです。
どの方法が正解というわけではなく、ふたりの生活スタイルや考え方に合った方法を選ぶことが何よりも大切です。
まずは話し合いの場を持ち、小さなステップから始めてみましょう。
それが、将来の安心とゆとりにつながっていきます。
こちらもCHECK
-

-
手書きとアプリ、家計簿はどっちが使いやすい?自分に合った家計管理の見つけ方
家計簿を始めてみたいけど、手書きとアプリ、どっちがいい? そんな疑問を持つ人は多いはずです。家計簿は継続が命。 だからこそ、自分にとって“使いやすいスタイル”を選ぶことが何よりも大切です。 この記事で ...
続きを見る